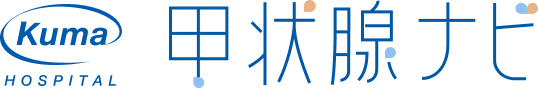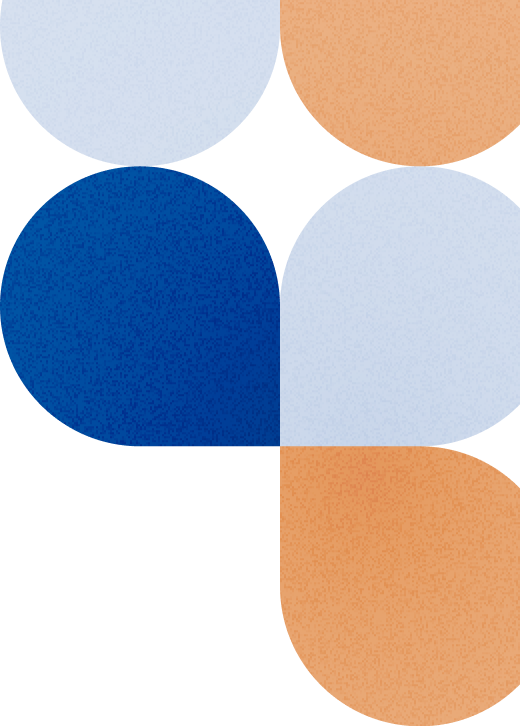
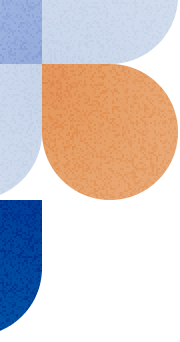
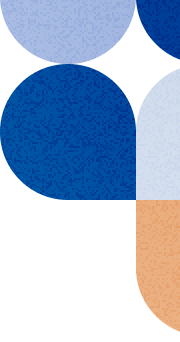
甲状腺ってなに?
「甲状腺(こうじょうせん)」って知っていますか?
聞いたことがある、という方でも、胃や肺などと違って、どこにあって、何をしている器官か、ということまで知っている人は少ないのではないでしょうか。甲状腺は、私たちの体の中でとても大切な役割を果たしている小さな臓器です。このページでは、甲状腺がどんな働きをしているのか、わかりやすく説明します。
Q1甲状腺とは?
甲状腺は、首の前側、ちょうど喉ぼとけの下あたりにあって、蝶々のような形をしています。重さ10~20g、サイズ45mm×40~50mmの小さな臓器です。やわらかく通常は外から触ってもわからないため、あまり意識することはありません。しかし、この「甲状腺」は、私たちが生命を維持するために必要不可欠なホルモンを作っています。
甲状腺が作るホルモンを「甲状腺ホルモン」といい、新陳代謝や細胞の成長を促す非常に重要な働きをします。甲状腺ホルモンが正常に作られて体内でうまく働くことによって、私たちの体は元気に動くことができるのです。
Q2甲状腺の病気ってどんな症状?
このように生きていく上でとても大事な甲状腺ですが、時に甲状腺が病気になってしまうことがあります。甲状腺の病気はいろいろありますが、「甲状腺ホルモンが過不足になるもの」と「甲状腺の一部が勝手に大きくなるもの」の2つに分けられます。ホルモンの過不足になるものの代表が「バセドウ病」や「橋本病」で、一部が大きくなるものに「甲状腺腫瘍」があります。
このうち、「バセドウ病」と「橋本病」は「自己抗体」ができてしまう、免疫機能の異常によって引き起こされる「自己免疫性甲状腺疾患」と呼ばれます。
自己抗体には自己組織を破壊するように作用するものと刺激するように作用するものがあります。自己免疫性甲状腺疾患になると、甲状腺ホルモンが多すぎたり、少なすぎたりして適切に生成されなくなります。「甲状腺ホルモン」の働きは全身に影響するため、作られる量が多すぎたり少なすぎたりすることで、あらわれる症状も多岐にわたります。他の病気と間違われることもめずらしくありません。
「甲状腺腫瘍」では甲状腺の一部が勝手に増殖して腫れてきます。遺伝性のものもありますが、多くのものは原因不明です。小さい内は触れませんが、ある程度以上に大きくなると自分で「しこり」として触れたり、見た目に塊状に見えたりすることがあります。腫瘍部分以外で甲状腺ホルモンが正常に作られますので通常、甲状腺機能に異常はありません(稀に甲状腺ホルモンを過剰に生成する腫瘍があります)。甲状腺腫瘍には「良性」と「悪性」がありますが、ほとんど(約9割)は良性です。
甲状腺の病気だからといって、必ずしも甲状腺のある首やその周辺に症状が現れるわけではありません。ご自身に当てはまるものがないか、チェックしてみましょう。
甲状腺の病気 チェックリスト①
甲状腺ホルモンが
多いときに出やすい症状
- 暑がり、多汗になる
- 体温が上がる
- 食べる量が増えても体重が減る
- 脈が速くなる
- 動悸・息切れがする
- 手・指先がふるえる
- 落ち着きがなくなる
- イライラしやすくなる
- 疲れやすくなる
- 不眠になる
- 下痢や軟便になりやすい
- 目(眼球)が出てくる
- 首が腫れる
- 月経不順になる(過少になることが多い)
代表的な病気:
バセドウ病 / 甲状腺機能亢進症
甲状腺の病気 チェックリスト②
甲状腺ホルモンが
不足したときに出やすい症状
- 寒がり、冷え症になる
- 運動しても汗をかかない
- 食事量は増えていないのに、
体重が増える - 脈拍が少なくなる
- 顔などがむくむ
- だるさ、疲労感を感じる
- 動作がにぶくなる
- 筋力が低下する
- 集中力が低下し、気力がなくなる
- 毛が抜けやすくなる
- 皮膚が乾燥する
- 声がかれる
- 便秘になりやすい
- 月経不順になる(過多になることが多い)
代表的な病気:
橋本病 / 甲状腺機能低下症
甲状腺の病気 チェックリスト③
甲状腺腫瘍があるときに
出やすい症状
- 首に「しこり」を触れる
- 首の一部が腫れる
- 声が嗄れる(腫瘍によって声帯を動かす神経が圧迫された場合)
- 首に圧迫感を感じる
- ものを飲み込みにくくなる
代表的な病気:
甲状腺腫瘍 / 甲状腺良性腫瘍 / 甲状腺悪性腫瘍(がん)
Q3甲状腺の病気かもしれない時はどうしたらいい?

バセドウ病や橋本病の診断は血液検査(甲状腺機能検査)が重要です。自己抗体の有無やシンチグラフィ検査といって甲状腺へのヨウ素などの集まり具合を調べる検査も必要になります。
甲状腺腫瘍は、超音波(エコー)検査が重要です。現在では検査技術が向上し、ミリ単位の微小な腫瘍も発見できるようになりました。良性か悪性(がん)かの診断に、腫瘍に細い針を刺して検査する「細胞診」が行われます。甲状腺腫瘍患者の方の多くが、自覚症状が現れる前に健康診断などの超音波検査で発見され、病院を受診しています。
甲状腺の病気は、ほとんどの場合、検査を受けることで重症化する前に発見できます。初期の自覚症状だけで判断することは非常に難しいため、気になることがあれば、お近くのかかりつけ医もしくは専門の医療機関に相談しましょう。
Q4甲状腺の病気は治る?
バセドウ病
バセドウ病の詳細な原因は不明で、現在の医療では残念ながらいわゆる「完治」はしない病気です。
症状が落ち着き、薬の投与などの治療を行わなくても甲状腺機能が正常化することを「寛解」といい、バセドウ病は「完治」ではなく、この「寛解」を目指して治療を行います。
抗甲状腺薬の服用を続けることなどで多くの人で症状が出なくなり、薬をいったん中止できる方は少なくありません。ただし、「完治」することはないため、薬の処方はなくなっても再発のリスクは残っています。そのため、定期的な経過観察によって再発していないかを確認し、再発の兆候が見られた場合には早い段階で対応することが大切です。
橋本病
橋本病もバセドウ病と同じく「完治」しない病気です。しかし、多く(約9割)の人は甲状腺機能は正常で、このような場合の治療は通常、不要です(稀に甲状腺が非常に大きくなった場合などは内服や手術が必要になることがあります)。
甲状腺機能が低下した場合の橋本病の症状は、甲状腺ホルモン薬内服によって消失するのが普通で、健康なときと変わらない日常生活を送ることができます。
ただし、この「甲状腺ホルモン薬」は橋本病によって不足している甲状腺ホルモン量を補うためのおくすりで、「橋本病を治す」ものではありません。そのため、適切な甲状腺ホルモン量を保つため、定期的に受診し、甲状腺の状態を確認しながら、内服を継続する必要があります。
甲状腺腫瘍
甲状腺腫瘍の大部分(約9割以上)は良性です。甲状腺の良性腫瘍は通常、治療の必要はありません。半年か1年に1度の経過観察を行います。多くの場合変化しませんが、稀に大きくなったり、悪性の可能性が否定できなかったりするような場合は手術が勧められる場合があります。
悪性腫瘍(がん)は他の臓器の腫瘍(がん)と同じく、手術で病巣を切除する治療を行います。甲状腺を全て切除した場合、甲状腺ホルモンを体内で作ることができなくなるため、甲状腺ホルモン薬を服用することが必要になります。
甲状腺がんの大部分(約9割)は「甲状腺乳頭がん」という、他のがんに比べて進行のスピードがゆるやかで穏やかな性格のものです。特に、1cm以下の小さな乳頭がんで気管や神経に近くないなどリスクの低い場合は、手術しない方が患者様の生活の質(QOL)を損なう可能性が低いと考えられるので「経過観察」が推奨されます。
いたずらに恐れることなく、まずはお近くの医療機関で相談してみましょう。
理解が深まる用語解説
ホルモン
体の恒常性維持のためいろいろな細胞の機能を調節する働きをもつ微量な物質です。内分泌腺という特殊な臓器で作られて、血液を通して全身に運ばれて作用します。主な内分泌腺には、下垂体や副腎、膵臓などがあり、甲状腺もそのうちの一つです。これらのホルモンは通常、「ネガティブ・フィードバック機構」によってバランスが保たれていますが、何らかの原因でこれが崩れると、健康に大きな影響を及ぼします。
甲状腺ホルモン
甲状腺でつくられるホルモンで、主に(1)細胞の新陳代謝を促進する、(2)交感神経を刺激する、(3)成長や発達を促進するなどの役割を果たしています。甲状腺ホルモンには「サイロキシン(T4)」と「トリヨードサイロニン(T3)」の2種類があります。下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)が甲状腺を刺激することで、甲状腺ホルモン(T4,T3)の分泌を促します。逆に、T4、T3が過剰に分泌されるとTSHが低下してT4、T3分泌を下げるように調整しています(ネガティブ・フィードバック機構)。
自己免疫性疾患
免疫は本来、自己を守るために異物を攻撃する働きをします。ところが、この免疫に異常が生じることによって、本来攻撃されるはずのない自身の臓器などが攻撃され、心身に支障をきたす病気を「自己免疫疾患」といいます。免疫に異常が発生する詳細な原因はわかっていません。そのため免疫異常そのものを治療することは困難なため、慢性的な病気と長く付き合っていくケースが多いのが現状です。
QOL(生活の質)
個人がどれだけ満足して生活しているかを示す指標です。医療の分野では、患者さんが病気や治療によってどのような影響を受け、その結果として生活の質がどのように変化するかを評価するために使われます。単に病気を治すことだけでなく、患者さんがどれだけ快適で充実した生活を送れるかを重視するため、例えば、がん治療を受けている患者さんの場合、治療の効果だけでなく、副作用による生活の質の低下も考慮されます。治療の選択肢を検討する際には、検査データだけでなく患者さんのQOLを向上させることが重要な目標となります。