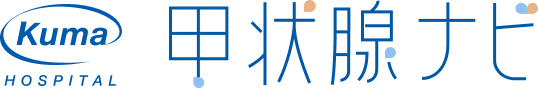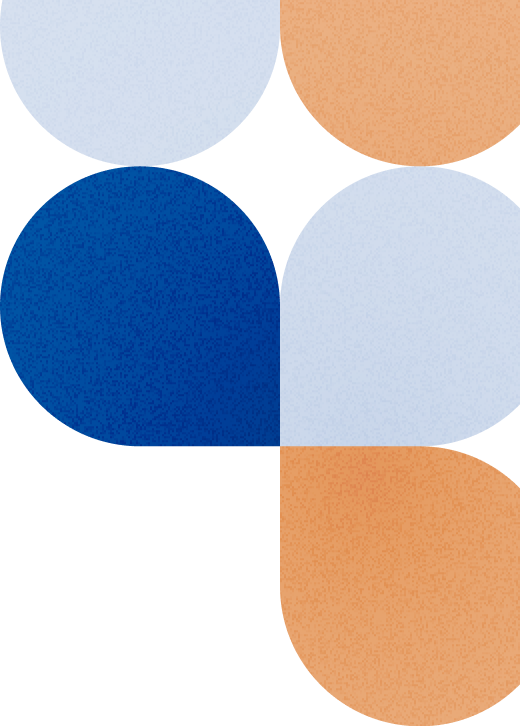
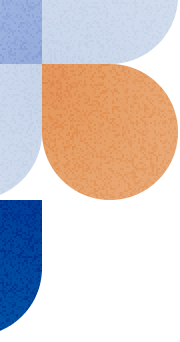
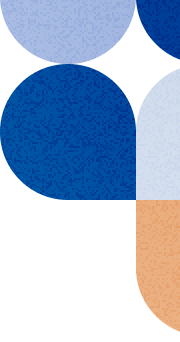
甲状腺がん
甲状腺がんは、甲状腺にできる悪性の腫瘍(しこり)のことで、甲状腺の周りの臓器を壊しながら広がったり(浸潤)、頸部のリンパ節にひろがったり(リンパ節転移)、あるいは離れた臓器に転移したり(遠隔転移)する性質があります。ただし、甲状腺にできる「しこり」のうち、9割は良性。たとえ悪性でも、甲状腺がんの多くは性格の穏やかな「がん」のため、必要以上に怖がる必要はありません。
さくっと解説!3分動画
症状
甲状腺がんは自覚症状のないことが多いです。腫瘍の大きさや位置によっては、声がかすれたり、首の違和感・圧迫感を感じたりすることがありますが、検診や別の病気の検査時に突然見つかるというケースがよくみられます。一部の種類を除いて、非常に発育がゆっくりの大人しいがんで、以下のデータに示される通り、年間死亡数が肺がんの40分の1と少なく、5年生存率が90%を超える治療成績のよさから、甲状腺がんで亡くなる人は他のがんに比べてかなり少ないです。
甲状腺がんのデータ
診断される数:年間約16,500人
女性に多い(男性約4,500人、女性約12,000人)
年齢別のピークは65-75歳
死亡数:年間約1,900人(男性約600人、女性約1,300人)
5年生存率:約95%(男性91%、女性96%)
参考:がん情報サービス(国立研究開発法人国立がん研究センター)*上記データは2025年3月参照
種類
甲状腺に発生する悪性腫瘍(がん)には大きく分けて5つの種類があります。
甲状腺乳頭がん
甲状腺乳頭がんは、甲状腺がんのなかで90%を占め、最もよくみられます。おとなしい性格のがんで、命にかかわることはあまりありません(10年生存率は約90%以上*1)。頸部のリンパ節に転移することはありますが、肺や骨などに遠隔転移することは少なく、乳頭がんそのものの増殖もゆっくりなので、慌てずに治療を進められます。
甲状腺濾胞がん
甲状腺濾胞がんは、甲状腺がんのなかで5%を占め、乳頭がんの次に多いがんです。このがんも増殖スピードはゆっくりですが、10年生存率は約85%*1と、乳頭がんより少しだけ悪くなります。一部の濾胞がんは遠隔転移することがありますが、頸部リンパ節への転移はまれです。
甲状腺髄様がん
甲状腺髄様がんは、甲状腺がんの中で1~2%と、まれながんです。乳頭がん・濾胞がんに比べて進行が速く、リンパ節・肺・肝臓などに転移することがあり、10年生存率は75%*1と濾胞がんより悪くなります。一部遺伝性のものがあり、遺伝学的検査を受けることで、遺伝性かどうかがわかります。
甲状腺低分化がん
甲状腺低分化がんは、甲状腺がんの中で1~2%と、まれながんです。乳頭がんや濾胞がんなどの「高分化がん」と「未分化がん」の中間に位置するがんです。進行が速く、離れた臓器に転移しやすい特徴があるため、注意が必要です。
甲状腺未分化がん
甲状腺未分化がんは、甲状腺がんのなかで1%と、大変まれながんです。進行が非常に速く、さらに甲状腺の周囲や離れた臓器への転移もみられます。1年生存率は20%以下*1。高齢者に多く、長年存在していた乳頭がんや濾胞がんが、未分化がんに変化することがあると考えられています。
甲状腺リンパ腫
リンパ腫は本来、リンパ節にできるものですが、まれに甲状腺に最初に発生することがあります。甲状腺にできるがんの中で2~3%と、比較的まれながんと言えます。この甲状腺リンパ腫は「橋本病」から発生することが多く、その場合、甲状腺が急速に大きく腫れて呼吸困難などを伴うケースもあります。60~70代の女性によくみられます。
*1:出典「甲状腺専門医ガイドブック改訂第2版(日本甲状腺学会編)」(診断と治療社/2018年)
原因
甲状腺がんの原因は、はっきりとはわかっていません。ごく一部のがんについては、遺伝性(家族性)のものがあります。
髄様がんの25~40%は遺伝性で、常染色体顕性遺伝(じょうせんしょくたいけんせいいでん)という形式で2人に1人の子供に遺伝します。RET遺伝子を調べる検査を受けることで、遺伝性かどうかがわかります。また、乳頭がんの2~5%にも家族性が認められていますが、原因となる遺伝子はまだ発見されていません。
また、小児期に他疾患に対する放射線治療を受けたり、チョルノービリ(チェルノブイリ)原発事故で被ばくしたりしたような場合に、数~数十年以上経過してから甲状腺がんが発生する可能性があるという報告もあります。
検査
がんの診断、がんの種類や性質を調べるために、「血液検査」や「超音波検査」「細胞診(穿刺吸引細胞診)」を行います。このほか、がんの甲状腺の周りへの拡がりや遠隔転移を調べるために「CT検査」を行います。必要に応じて頸部X線検査(レントゲン検査)、MRI検査、PET検査を行うこともあります。
超音波検査(エコー)
超音波検査は、がんの有無だけでなく、その数、大きさ、周りへの拡がり具合状態などを確かめるのに不可欠な検査です。さらに、リンパ節転移の有無やその転移の可能性を調べるためにも用いられます。
細胞診(穿刺吸引細胞診)
細い注射針を腫瘍に刺し、細胞を直接採取する検査です。通常の採血の注射針と同じ太さの針を使用するため、痛みは血液検査と同程度で、麻酔を行う必要もありません。乳頭がんや未分化がん、髄様がん、リンパ節への転移の診断には非常に有用ですが、濾胞がんの診断には不向きです。
治療
甲状腺がんの治療は、主に「手術」「放射線治療」「薬物治療」の3種類があり、症状や身体の状態、年齢やその他の状況を考慮して、医師と相談しながら決定します。
多くの場合は、手術が基本的な選択となりますが、腫瘍の大きさが小さく(1cm以下)、リスクが低いと考えられる場合には、すぐに手術を行わず、定期的な通院で超音波検査を継続する「甲状腺微小がんの積極的経過観察」を推奨しています。
手術
甲状腺がんの手術は、がんのある場所や大きさ、リンパ節転移の有無、遠隔転移の有無などによって、切除する範囲を決定します。
甲状腺に隣接するリンパ節への転移が明らかもしくは疑いの強いものについては、甲状腺を切除する際にリンパ節の切除(頸部リンパ節郭清)もあわせて行います。
アイソトープ治療(放射線治療)
乳頭がんや濾胞がんの細胞は、正常な甲状腺細胞と同じくヨウ素を吸収します。この性質を利用して、医療用放射性ヨウ素(アイソトープ)のカプセルを服用し、転移や再発を防ぐ治療法です。甲状腺が残っていると、がん細胞よりも先に健康な甲状腺が被ばくしてしまいますので、甲状腺全摘術で甲状腺をすべて切除した方が対象になります。
なお、甲状腺全摘術を行っても、甲状腺組織がわずかに残ることがあり、これを破壊して甲状腺疾患の再発を防ぐ「アブレーション」や、がんの遺残が疑われながらも画像検査等で確認できない場合に行われる「アジュバント療法」もこれに含まれます。
分子標的薬(薬物治療)
一部のがん細胞のみがもつ特定の分子を標的とする治療薬です。甲状腺がんにおいて、従来の抗がん剤と比較してより効果が期待できる場合があります。多くは、価格が高額で重篤な副作用のリスクも否定できないことから、手術やアイソトープ治療の効果が期待できない症例で使用します。
まとめ
- 甲状腺がんの大部分は、乳頭がんと呼ばれる性格の大人しい危険性の少ないがんです。
- 甲状腺がんは、超音波検査、細胞診、血液検査などの結果から診断されます。
- 甲状腺がんの治療は手術が基本で、がんの位置や大きさ・転移などを考慮して切除範囲を決めます。
- サイズが小さく高リスクの因子がない「低リスク甲状腺微小がん」は、経過観察を選択することも可能です。
理解が深まる用語解説
遺伝学的検査(遺伝子解析)
遺伝学的検査とは、遺伝子や染色体の解析によって、遺伝性の病気の発症や、生まれ持った病気のなりやすさや体質などを調べる検査です。甲状腺・副甲状腺の病気に関わる遺伝子には「RET遺伝子」「MEN1遺伝子」などがあります。
RET遺伝子
RET遺伝子とは、がんの発生や増殖に関わる「がんドライバー遺伝子」の一つです。このRET遺伝子に変異が起こると、甲状腺がんや肺がんを引き起こす可能性があります。隈病院では、このRET遺伝子を遺伝学的検査で調べることで、甲状腺髄様がんと多発性内分泌腫瘍症2型(MEN2)の診断に役立てています。
甲状腺微小がんの積極的経過観察
1993年に隈病院3代目院長宮内昭が「低リスクの甲状腺微小乳頭がんは手術の合併症によるリスクを避け、経過観察を選択」することで、がんの進行をモニターしつつ患者の生活の質に配慮する治療方針を提唱しました。それから30年間に蓄積したデータを活用した研究成果は国内外で注目され、現在、日本および米国のガイドラインにもこの「積極的経過観察」が採用されています。
アイソトープ治療
アイソトープ治療(131I内用療法)は、甲状腺がヨウ素を取り込む性質を利用して、医療用放射性ヨウ素(131I)のカプセルを服用し、組織内部から放射線照射を行う治療法です。「RI治療」「放射性ヨウ素内用療法」と呼ばれることもあります。他臓器への影響がきわめて少なく、副作用や合併症のリスクも低いです。そのため、欧米では日本に比べてより一般的な治療方法と捉えられています。特殊な装置や設備をそろえる必要があるため、日本では実施可能な医療機関が限られています。
甲状腺腫瘍診療ガイドライン
甲状腺腫瘍診療ガイドラインは、日本内分泌外科学会と日本甲状腺外科学会が2010年に公開した第1版から、2018年の第2版を経て、2024年4月に改訂第3版が公開されました。診療の標準化と、エビデンスに基づく適切な情報提供による患者の意思決定の実現を目的とした本ガイドラインの作成には、隈病院で行った多くの臨床研究データが役立っています。成人患者を対象として、甲状腺腫瘍の初期評価及びその診断と治療ならびに経過観察といった医療場面において、医療者による活用が期待されています。ガイドラインはウェブサイト等で一般に公開されており、だれでも閲覧することができます。