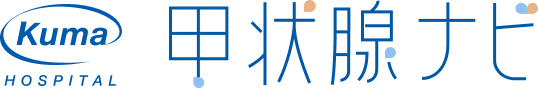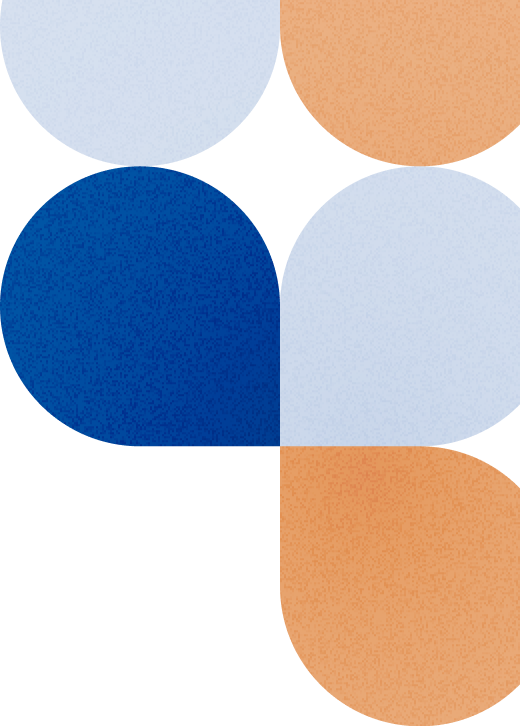
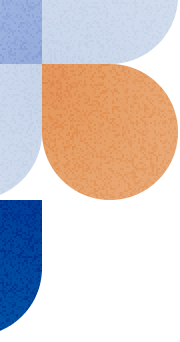
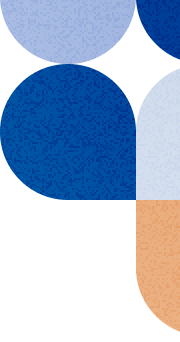
甲状腺微小乳頭がんは『積極的経過観察』を推奨しています
- #低リスク甲状腺微小がん
- #治療
- #診療ガイドライン
- #隈病院が推奨する医療
「がんを切らない」という選択肢
がんが見つかると、一般的には「すぐに手術しなければ!」と考えられることが多いかと思います。
しかし、甲状腺がんのうち、低リスクの甲状腺微小がんの場合には、隈病院が1993年から2020年までに蓄積した3,200件以上のデータ検証をもとに、
①手術をしないで経過観察しても9割以上は増大・進行しないこと
②経過観察中に少し大きくなってから手術した場合でも、最初の時点で手術した場合でも、甲状腺がんが原因で死亡した人はゼロであったこと
③最初の時点で手術を選んだ群の方が経過観察を選んだ群より、声帯神経や副甲状腺の損傷などの不都合事象の頻度が高いこと
などが、明らかになりました。
そこで隈病院では、この研究成果に基づき、低リスク甲状腺微小がんの場合は積極的経過観察を第一選択としてご提案しています。
こうした研究成果は国内外で注目され、この「甲状腺微小がんの積極的経過観察」は、日本内分泌外科学会の2010年の甲状腺腫瘍診療ガイドラインに世界で初めて採用され、2018年には積極的に推奨されました。さらに、2021年には同学会と日本甲状腺学会がこの取扱い方法を支持し普及するため、それぞれがConsensus statementとPosition paperを英文で発表しました。世界でも最も権威がある「アメリカ甲状腺学会」の2015年の甲状腺腫瘍取扱ガイドラインでも消極的に記述されましたが、2025年の改訂版ではより積極的に推奨されるとの情報です。
低リスク甲状腺微小がんとは
最大径が1cm以下の甲状腺がんを「甲状腺微小がん」と呼びます。
以前から、他の病気で亡くなった方の解剖を行うと、微小な甲状腺がんが高頻度で見つかることが知られており、超音波検査で容易に発見することができる3㎜以上の甲状腺がんは3~5%の高頻度で見つかると報告されています。実際に、香川県立がん検診センター(現・香川県立中央病院がん検診センター)の研究では、乳がんの健診のため受診した成人女性に超音波検査を用いて甲状腺がんの検診を実施したところ、受診者の3.5%に甲状腺がんが見つかったと報告されました。つまり、多くの方が、甲状腺微小がんの存在に気が付かないまま過ごしているのです。
とはいえ、「がん」である以上、転移の心配があるのは当然のことです。甲状腺がんの場合、微小がんであっても、実際に手術を行うと実は30~40%の患者さんにリンパ節に顕微鏡的な微細な転移が見つかります。ところが、この転移した「がん」は、顕微鏡でようやく発見できる程度のごく小さながんであり、手術で摘出しなくてもほとんど成長せずに生命への影響が極めて小さいことが明らかになっています。
甲状腺がんが増加している
甲状腺がんが近年、世界的に増えていることをご存知でしょうか。
アメリカでは1973~2002年の30年で罹患率はおよそ2.4倍に上昇(Davies L, Welch HG. Increasing incidence of thyroid cancer in the United States, 1973-2002. JAMA. 295:2164-7, 2006)しましたが、増加したのは小さい乳頭がんであり、甲状腺がんによる死亡は増加しませんでした。国の方針として積極的に超音波検査などで甲状腺がんの健診を行った韓国では1993年〜2011年の18年で甲状腺がん患者が約15倍にまで増加しました(Ahn HS, Kim HJ, Welch HG.: Korea’s thyroid-cancer “epidemic”- screening and over diagnosis. N Engl J Med. 2014 Nov 6;371(19):1765-7.)が、甲状腺がんによる死亡率には変化がなく、手術による合併症に苦しむ人が増加したことがKorea’s thyroid-cancer epidemic (韓国における甲状腺がんの流行)と皮肉っぽく報告されています。これは、がんを発症する患者の絶対数が増えたのではなく、エコーやCT、PET、MRIなどの画像検査法の発達や受診数の増加によって、これまでは見つからなかった最大径1cm以下の微小がんでも見つかるようになったことが主な原因と考えられています。
甲状腺がんはいくつかの種類に分類されますが、なかでも実際に増加しているのは、最も多くまた画像診断で発見・診断されやすい乳頭がんという種類です。この乳頭がんはエコーガイド下穿刺吸引細胞診という手法を用いると、3㎜程度の微細ながんまで発見し診断することができます。
実際に、甲状腺がんの発見頻度は増えているにもかかわらず、人口当たりの甲状腺がんによる死亡率は変化していません。つまり、ほとんどの甲状腺微小乳頭がんは患者の死亡につながっていない、といえます。
甲状腺微小乳頭がんの積極的経過観察を、隈病院が世界で初めて採用
こうした事実を総合的に検討し、いち早く「甲状腺微小乳頭がんの大部分は、増大進行しない無害ながんである可能性が高い。全ての微小がんに手術をすることは益よりも害の方が大きいだろう。しかし、一部の微小がんは増大するものもあるだろう。経過を見て増大・進行する場合には手術をすれば十分に対応できるだろう。」と考えたのが、隈病院3代目院長・現名誉院長の宮内昭医師でした。宮内医師の提案により、1993年、隈病院が世界で初めて「甲状腺微小がんの非手術経過観察」を採用し、この臨床的取組みを開始しました。
そして、これまでに5,600人を超える患者さんのデータを蓄積・分析することで、2023年時点では、以下のようなことがわかってきました。
10年間の経過観察中、95%が「がん」の大きさに変化なし
経過観察を開始し10年経った時点で、がんが3mm以上大きくなったのは5%の方のみで、残りの95%の方のがんは大きさが変化しないか、一部では縮小していることがわかりました。また、小さなリンパ節転移を生じた人は1%のみでした。
がんが大きくなったりリンパ節転移が出現したりした時点で手術を行えば、その後の再発率は直ちに手術を行った群と同様に極めて低頻度であり、甲状腺がんのために亡くなった方はいませんでした。
「リンパ節転移」は経過観察の失敗?
経過観察を選択した患者さんの1%には、リンパ節転移がみられました。最初に手術をすれば防げたのでは?と思えるかもしれませんが、頸部外側のリンパ節転移は、微小がんの手術(甲状腺葉切除と気管周囲のリンパ節郭清)では予防できません。
この場合、最初に手術してもリンパ節転移を妨げられず、リンパ節転移が確認できた後に2度目の手術を受けなければならなくなります。手術を複数回受ければ、その分手術にともなう障害や合併症のリスクが増えることとなり、場合によっては患者さんの生活の質が大きく損なわれる恐れもあります。
手術または経過観察、いずれを選択しても甲状腺がんによる死亡者はゼロ
研究期間中に隈病院で微小甲状腺がんと診断された5,646人を対象に分析したところ、そのうち手術を選択した方(以下「直ちに手術群」)は2,424人(43%)、積極的経過観察を選択された方(以下「経過観察群」)は3,222人(57%)でした。
「直ちに手術群」を選んだ2,422人のうち、がんが再発した人は26人(1.1%)で、再手術を行った後も再発や死亡は確認されていません。また、「直ちに手術群」うち82人が、後日他の病気で亡くなられています。
「経過観察群」を選んだ3,222人のうち、その後394人の方が「気持ちが変わった」、「併存した甲状腺結節や副甲状腺の病気」などのさまざまな理由で手術を受けました。そのうちの3人(0.8%)が再発しましたが、再手術の後は現在まで再発も死亡も確認されていません。手術を受けず経過観察を継続された2,828人中の36人の方が他の原因で死亡しましたが、残りの人はご存命で微小がんの進行はありません。
このように、手術をした場合でも、しなかった場合でも、甲状腺がんが原因で死亡した方は、対象となった5,646人ではゼロという結果です。
経過観察を選択することで、声帯麻痺や副甲状腺機能低下症を回避
甲状腺の手術をすると、声帯麻痺や副甲状腺機能低下症のリスクが生じる一方で、経過観察を選択した場合には、これらのリスクがほとんど生じていないことが、隈病院のおよそ30年にわたる研究によって明らかになりました。
【一過性声帯麻痺】
「直ちに手術群」8.7% / 「経過観察群」0.9% の頻度で発生
「永続性声帯麻痺」「直ちに手術群」0.9% 「経過観察群」 0%
【一過性副甲状腺機能低下症】
「直ちに手術群」20.8% / 「経過観察群」2.1% の頻度で発生
【永続性副甲状腺機能低下症】
「直ちに手術群」1.4% / 「経過観察群」0.2% の頻度で発生
これらの臨床データの裏付けにより、この「低リスク甲状腺微小がんの積極的経過観察」は国内外で高く評価され、現在では日本ならびにアメリカ甲状腺学会の甲状腺腫瘍診療ガイドラインに採用されています。
甲状腺ホルモン薬を服用して血中TSH値を低めに保つと微小がんの進行を抑制
皆さんの血液中にはTSH(甲状腺刺激ホルモン)が流れています。このホルモンは血液中の甲状腺ホルモンが低下すると多く分泌され、逆に甲状腺ホルモンが多くなるとTSHは少なくなります。この様にして、血中の甲状腺ホルモン値がほぼ一定となるように調節されています。TSHは正常の甲状腺細胞を刺激して甲状腺が大きくなります。甲状腺乳頭がんもTSHの刺激を受けて大きくなる傾向があります。従って、甲状腺乳頭がんの手術後には再発のリスクに応じて、血中TSHを低めに保つように甲状腺ホルモン薬の量を調節します。甲状腺微小乳頭がんも同様に血中のTSHを低めに保つとがんの増大・進行が抑制されるのではないかと、宮内名誉院長他数名の医師が考え、患者さんに説明の上で、少量の甲状腺ホルモン薬を服用して頂きました。10年間での腫瘍進行率は、非投与群では6.1%でしたが、投与群では2.9%と半分以下となりました。また、腫瘍の体積の増大率を詳しく調べると、甲状腺ホルモン投与後は投与前に較べて明らかに増大率が低下していました。今後、この様な試みが認知され広まってくるかも知れません。